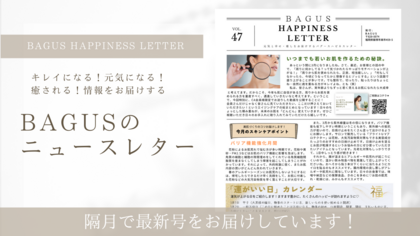受付時間: (平日)10:00〜17:00 (土曜・祝日)11:00〜17:00 定休日: 木曜日・日曜日
- ホーム
- BAGUSブログ
- 季節のおすすめセルフケア
- 冬の土用にやるべきこと・避けるべきこと〜心と体を守るセルフケア〜
冬の土用にやるべきこと・避けるべきこと〜心と体を守るセルフケア〜
2025/01/1718日間で心と体の調子をリセット!季節の変わり目を健やかに過ごす冬の土用のポイント 冬の土用は、新しい季節を迎えるための準備期間。心身を整える具体的なアプローチを通じて、忙しい毎日の中でも取り入れやすい温活やリラックス法をご提案します。

1月18日(土)から冬の土用に入ります。
季節の変わり目、なんだか体調が優れない、心が落ち着かない…そんなことはありませんか?
冬の土用は、特に気圧の変化や寒さが厳しくなることで体調やメンタルに影響が出やすい時期です。
このブログでは、そんな冬の土用を健やかに乗り切るための具体的なセルフケア方法や、避けるべき行動をわかりやすくお伝えします。
ぜひ、忙しい毎日の中に少しの癒しとケアを取り入れてみてください。
土用って何?その影響と過ごし方


土用とは季節の変わり目のこと
土用とは、立冬、立春、立夏、立秋の前の18日間を指します。
この期間は、自然界も次の季節に移行する準備をする時期で、"土の気"が強くなるとされています。
特に土用は、気圧の変化が激しく、体調を崩したり、心が不安定になることが増えると言われています。
2025年の冬の土用は、1月18日から2月2日まで。
この期間は、心身をいたわり、次の季節に向けて整えることが大切です。
土用期間中の注意点
昔から、土用は"土の神様の衣替えの時期"とされ、家の造作や引越し、旅行、土いじりなどを避けた方が良いと言われています。
これは、体や心を無理させず、休息に充てる期間として解釈することができます。
この時期には、見えない"気"の影響を受けやすいとも言われ、普段しないようなミスをしたり、
気持ちが落ち込んだり、不調を感じることも。
そんな時は、「これは土用のせい」と考え、無理をせずに過ごすことが大切です。
冬の土用におすすめのセルフケア

土用には季節ごとに干支が割り当てられており、冬は「未(ひつじ)」です。
体調を崩しやすい季節の変わり目にあたる為、季節にあった食材を取り入れ養生する慣わしで、
冬は「土用の未の日」にちなんで、「ひ」のつくものや「赤い」ものを食べると縁起がよいとされています。
ひのつく食べ物: ひらめ、ひじき、ひき肉など
赤い食べ物: りんご、マグロ、イチゴ、トマト、唐辛子
また、冬の土用期間には、体を温め、免疫力を高めるために以下のような食材を取り入れてみましょう。
香辛料: シナモン、胡椒、山椒(鍋やスープに加えるのがおすすめ)
腸内環境を整える食材: 野菜やきのこ類(大根、人参、ごぼう、里芋、白菜)
解毒作用のあるシソ: インフルエンザなどの風邪予防や精神安定、抗炎症、整腸作用が期待できます。特に赤い食材のマグロと一緒に摂ると縁起が良く、オススメです。
漢方が教える冬の特徴と対策


漢方では、冬を「閉蔵」と言い、内向的になりがちで、体が良いものも悪いものも蓄えやすい時期とされています。
このため、お正月の胃腸の疲れが出やすい時期とも重なります。
腸内環境を整える野菜やきのこ類を意識的に摂取し、健康を保ちましょう。
また、東洋医学では、食べ物には体を温めるもの、冷やすもの、どちらでもないものがあることが2000年以上の歴史の中で研究されてきました。
体を温める野菜: ネギ、ニンニク、しそ、にら、玉ねぎ、かぼちゃ、らっきょう、しょうが
タンパク質源: 鶏肉、牛肉、豚肉(免疫細胞の原料となるため重要)
魚類: エビ、鯵、秋刀魚、マグロ
特にエビは、冬に弱る腎の働きを助け、体を温める効果があります。
例えば、香辛料を加えた参鶏湯や野菜たっぷりのスープは、体を芯から温める効果があります。
手軽に取り入れられる温活メニューとして、ぜひお試しください。
土用時期におすすめの入浴法

冬の土用の冷え対策には、入浴も効果的です。心身ともにリフレッシュできるおすすめの入浴方法をご紹介します!
不調を感じたら、バスタブに塩やお酒を加えて心身の浄化。特に塩は体を温めてくれます!
もし、バスタブにお塩を入れることができない場合には、一掴みのお塩を頭や肩、足に乗せてシャワーで洗い流してみてください。 これだけでも不思議とスッキリします!
エッセンシャルオイルの力を借りる〜土用時期におすすめなのは?〜


ユーカリ: 鼻や喉の炎症を抑え、呼吸を楽にしてくれる効果が期待できます。
ペパーミント: 喉の不快感を和らげ、偏頭痛の緩和やストレス軽減にもおすすめ。
自宅でもアロマディフューザーを活用し、心地よい空間を作ってみてくださいね。
私の体験から学んだ健康の大切さ


2024年末、家族がインフルエンザにかかったことで私自身も体調を崩し、年末年始を通して健康の大切さを痛感しました。
この経験を通じて、2025年は健康やウェルネスをテーマにサロンづくりを進めていきたいと考えています。
冬の土用は特に、心身を労わる期間として意識することが大切です。
サロンでも、体調管理や癒しに役立つアイテムやサービスをご提案していますので、ぜひ色々とご相談いただけたらと思います♡
まとめ


冬の土用は、心と体のバランスを整える絶好のチャンスです。
今回ご紹介したセルフケアや温活アイテムを日々の生活に取り入れ、無理なく健康を守りましょう。
さらに詳しい情報やサロンでのケアについては、お気軽にお問い合わせください。
ブログの内容も参考にしていただければ嬉しいです♡
-
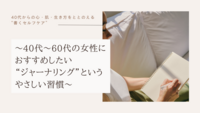 40代〜60代の女性におすすめしたい“ジャーナリング”というやさしい習慣
40代からの心・肌・生き方をととのえる“書くセルフケア” 連日暑い日が続き、もはや何もしたくない…。夏は、暑い
40代〜60代の女性におすすめしたい“ジャーナリング”というやさしい習慣
40代からの心・肌・生き方をととのえる“書くセルフケア” 連日暑い日が続き、もはや何もしたくない…。夏は、暑い
-
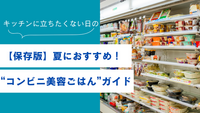 【保存版】夏におすすめ!キッチンに立ちたくない日の“コンビニ美容ごはん”ガイド
ゆるっと続く、40代からの“食べる美容習慣” こんにちは、BAGUSの山下です😊暑さと湿気で疲れが出やすいこの
【保存版】夏におすすめ!キッチンに立ちたくない日の“コンビニ美容ごはん”ガイド
ゆるっと続く、40代からの“食べる美容習慣” こんにちは、BAGUSの山下です😊暑さと湿気で疲れが出やすいこの
-
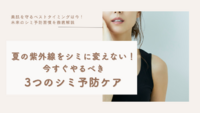 夏の紫外線をシミに変えない!今すぐやるべき3つのシミ予防ケア
美肌を守るベストタイミングは今!未来のシミ予防習慣を徹底解説 こんにちは。業界歴20年、エイジングケア専門サロ
夏の紫外線をシミに変えない!今すぐやるべき3つのシミ予防ケア
美肌を守るベストタイミングは今!未来のシミ予防習慣を徹底解説 こんにちは。業界歴20年、エイジングケア専門サロ
-
 【衝撃】6ヶ月でここまで変わる!美容整形級ビフォーアフター✨
「美容整形までは考えてない…でもなんとか抗いたい」そんな方はぜひご覧ください! 美容整形までは考えてない…でも
【衝撃】6ヶ月でここまで変わる!美容整形級ビフォーアフター✨
「美容整形までは考えてない…でもなんとか抗いたい」そんな方はぜひご覧ください! 美容整形までは考えてない…でも
-
 不調なのは“自分のせい”じゃなかった!秋のセルフケア処方箋
【五行タイプ診断つき】性格・季節別うまくいく人の漢方習慣 「なんとなく気持ちが落ち込みやすい」「呼吸が浅くて、
不調なのは“自分のせい”じゃなかった!秋のセルフケア処方箋
【五行タイプ診断つき】性格・季節別うまくいく人の漢方習慣 「なんとなく気持ちが落ち込みやすい」「呼吸が浅くて、